バイスティックの7原則は、援助関係の基本原則です。
バイスティックの7原則は次の通りです。
1個別化
2意図的な感情表出
3統制された情緒的関与
4受容
5非審判的態度
6自己決定
7秘密保持
バイスティックの7原則は、フェリックス・P・バイスティック(アメリカの社会福祉学者)が
1957年に出版した「ケースワークの原則」で提唱した援助関係の基本原則です。
このバイスティックの7原則は、信頼関係構築の方法であり、介護の現場でも応用することができ、利用者との関係性を深めることにも繋がります。
また、バイスティックの7原則は、介護福祉士や、社会福祉士の国家試験では、具体的な技法や事例が頻出されています。
この記事を読めば、より質の高いケアが提供できるようになり、利用者との関係性が深まります。介護職として成長したい方、試験を受ける予定がある方は、ぜひ参考にしてください。
筆者:たかはしポム太郎
資格:介護福祉士、介護支援専門員、認知症ケア専門士、キャラバン・メイト、登録販売者、チームオレンジコーディネーター研修修了、ユニットリーダー研修修了、認知症チームケア推進研修修了、認知症介護実践リーダー研修修了
私は介護の現場で働きながら、介護や認知症の研修を開催や、情報発信をしています。10年間の介護現場での経験、資格取得等で培った知識を発信していきます。介護や認知症について不安を抱いている方々に役立つ情報をお届けできればと思っております。少しでも不安が解消され、今抱えているお悩みに寄り添えたら嬉しいです。
バイスティック7原則
① 個別化
個別化とは、利用者をパターン化せず、利用者ひとりひとりの性格や生活歴に合わせたケアを行うことです。
例えば、「お年寄りは和食が好き」と決めつけて全員に毎日和食を提供してしまうと、洋食が好きな高齢者は、満足できません。
実際には、パン派の方や、ハンバーグカレーが好きな方もいます。
生活習慣や趣味、本人の希望、嗜好等、個人の違いを把握し、ひとりひとりに合わせたケアを行うことが重要です。
② 意図的な感情表出
意図的な感情表出とは、利用者のどのような感情も受けとめ自由な感情を引き出すように関わることです。
利用者が思っていることを、遠慮なく話せる環境や雰囲気を整えて、話しやすい態度を示すことが大切です。
③ 統制された情緒的関与
利用者の感情に引きずられることなく、冷静に自身の感情をコントロールし、適度な距離感で接することが大切です。
親身に接するのは大切なことですが、親身になりすぎると、利用者が依存してしまうことがあります。
利用者の感情に共感しながらも、客観的な視野で関わり、感情移入せずに、冷静に対応することが重要です。そのためには介護者自身が自分の感情に向き合い、自己覚知することも大切です。
共感と同情を分けて、事実を解釈し、状況を判断して言動を伝えることが大切です。
④ 受容の原則
受容とは、利用者のありのままを受け入れることです。
利用者の考えや価値観を否定せず、そのまま受け止めることが大切です。
利用者が事実と異なることを言っていても、決して否定せず、共感し、ありのままを受け入れましょう。
⑤ 非審判的態度
正しい正しくない、良い悪いという判断を一方的にしないことが重要です。
最終的な問題解決は利用者自身で行なうもので、介護者は利用者の考えや行動を判断せず、あくまでもサポートする立場であることを理解する必要があります。
決めつけず、利用者の価値観を尊重することが大切です。
⑥ 自己決定
自分のことは自分で決めるという考え方です。命令的な指示はせず、利用者の自己判断を促し、利用者の自己決定を尊重することが重要です。
介護が必要な方でも、利用者ができる範囲で、自分で選び、自分で決めることが大切です。
入浴後の着替えを職員が決めてしまうのではなく、利用者自身に選んでもらう等、介護の現場でも活かせる場面はたくさんあります。
⑦ 秘密保持
利用者の情報を漏らさない、プライバシーを守るということです。
利用者の個人情報やプライベートな話を勝手に他人に話さないことが大切です。
飲み会等、介護者のプライベート場面であっても、利用者の個人情報を漏らしてはいけません。
介護の仕事は、単に「お世話をする」だけではなく、利用者の心に寄り添うことが大切です。
この7原則を意識することで、利用者も介護者も 心地よく過ごせる環境 を作ることができます。
終わりに
バイスティックの7原則は、介護現場で 利用者との信頼関係を築き、質の高いケアを提供するために必要な考え方です。
介護は「正解がない」からこそ、日々の小さな工夫がとても重要です。
ぜひ、バイスティックの7原則を覚えて、介護現場で活用してみてください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。


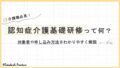
コメント